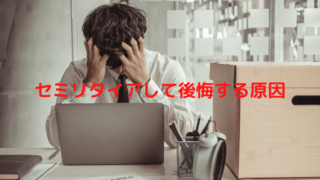前回の記事で収入1馬力の妻が退職を考えていること、その言動を受けた主夫である私の考えを記事にしました。
今回の記事は金銭的な話になります。
家計のCFO(最高財務責任者)である私が妻の退職に対して取った行動と妻へのプレゼン、妻の反応についてご紹介します。
過去の年間支出から生活費の確認を実施
まず家計簿の正確なデータが残る2017年~2022年までの年間支出と各支出項目(食費や教育費など)の分析を行いました。
そして最低限の年間生活費を設定しました。
また妻が退職すると家賃補助がなくなり、住宅費がアップするので、それも加味して以下の内容について検討しました。
①過去のデータから「最低限の生活費」を設定
②退職により変動する項目を設定
③「最低限の生活」、「節約生活」、「現在の生活」などの生活費を設定
④③の各生活について必要な年間支出額を把握
どの生活を実行するか?覚悟はあるのか?
妻退職後の生活をどうするのか?
最低限の生活、節約生活、現在の生活と同等水準なのかを妻と相談しました。
それぞれにかかる生活費と併せて年間でどれくらいの余裕(プラスα分)が欲しいのを検討しました。
このような具体的な生活を考えても「辞めたい」が勝つなら、次は収入についての話し合いです。

妻もセミリタイアした後に必要な収入額をきちんと把握する
妻退職後の生活費が決定すれば、次はその生活費を稼ぐ手段を考えていきます。
わが家には現在約120万円の配当金、24万円の児童手当があります。
合わせて144万円です。
設定した生活費から144万円を引いた金額を稼ぐ必要があります。
それを夫婦でどう分担するのか話し合いました。
また労働でカバーできないのなら、配当収入を増やすという手段もあります。
この辺りは妻はほぼ知識がないので私の判断となりますが、説明して夫婦の意思決定をするという形になりますね。
収入と同じようにセミリタイア後の働き方についても相談する
例えば私が企業に再就職して、妻がパート勤務するにしても、お互いが企業に属する身となり、今のような自由は無くなるでしょう。
それが家族にとってプラスとなるのか?
セミリタイアする意味があるのか?ということに繋がります。
子ども達がもう少し大きくなるまで、せめて第2子が小学生になるまでは収入は足りなくても少し自由な働き方でというのも話し合いました。
新NISA制度を活用し、あと数年で配当金を年間200万円まで持っていく。
色々な話が出ました。
様々なプランを話し合いました。
6月中にプランを作成し、順次実行していく予定です。