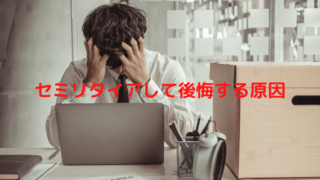小さい子供がいる家庭にとって遺族補償は考えたことがある人がほとんどでしょう。
本記事ではわが家の遺族補償の考え方と実際の遺族補償を記事にしました。
わが家はの家族構成は36歳夫婦+未就学児2人です。
私は収入があまりありません。
早速私が死んだ場合、妻が死んだ場合でシミュレーションしてみました。
セミリタイア主夫が死亡した場合の遺族補償
私は現在、ほぼ専業主夫状態の個人事業主で、妻の扶養に入っています。
国民年金の第3号被保険者であり、厚生年金には加入していないという状態です。
私が死亡した場合、妻はどんな補償を受けられるのでしょうか?
まず子を持つ親は基本的に遺族基礎年金を受給できます。
また生命保険にも加入しており、60歳まで毎月10万円(年額120万円)の補償が受けられます。
①遺族基礎年金
基本額78万円+子の加算額22万円×2人=120万円
(子どもが18歳の3/31まで支給される)
②生命保険:年額120万円
妻が60歳になるまで支給(25年間=3000万円)
私が生存している場合は収入がゼロ、死んだ場合はこのように年間240万円のお金が入ってきます。(子どもが18歳になるまで)
さらに配当金が毎月10万円程度ありますから、しばらくは毎月30万円程度の収入がある予定です。
私はこれで十分だと考えています。
妻は働いていますし、実家のサポートも受けられます。
続いて、妻が死んだ場合のシミュレーションです。
妻は現在収入の大黒柱ですからね。どんな補償にしているかをご紹介します。
セミリタイア主夫の妻が死亡した場合の遺族補償
①遺族基礎年金(私と同じ)
基本額78万円+子の加算額22万円×2人=120万円
(子どもが18歳の3/31まで)
②遺族厚生年金
600万円(平均年収)×0.5481×300×3/4=74万円(年額)
(子どもが18歳の3/31まで)
③生命保険:年額120万円
(私が60歳になるまで)
④会社の補償:年額48万円(毎月4万円)
(子どもが18歳になるまで)
*②遺族厚生年金は夫である私は受給権なし(55歳未満のため)
→子どもに支給
(平均標準報酬額×0.5481×被保険者期間の月数*×3/4を支給)
*300月に満たない時は300月で計算
子どもが18歳になるまではおおよそ30万円/月の収入があり、配当金も合わせると40万円/月の収入が見込めそうです。
これだけあれば、私が働けなくても生活に問題ないです。
私とは違い、遺族厚生年金が年額74万円、会社の遺族補償が年額48万円あります。
これは地味に大きい補償です。
生命保険の前に公的補償、会社補償を知る
生命保険などを考える時に公的な遺族年金(遺族基礎・遺族厚生年金)の額を把握しておくことはとても大事です。
さらに大企業であれば、福利厚生の一環として、独自の遺族補償制度を定めている場合もあり、確認が必要です。
これらの補償をきちんと把握した上で、足りない補償額を民間の生命保険で補うことが最も合理的だと思います。